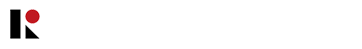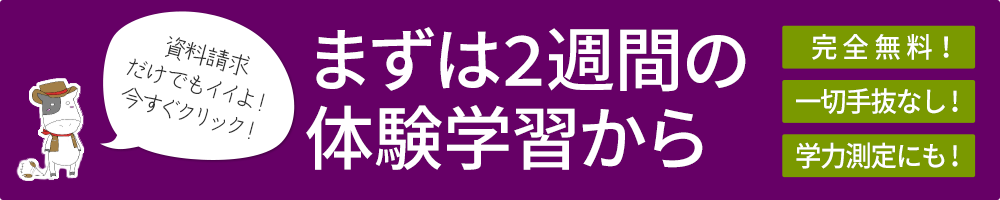坪木の教育論③:公教育の迷走と失政
ところが、公教育の現場では時代の要請に全く逆行する施策が実施され続けた。いわゆる「ゆとり教育」だ。大雑把に言って、現在の公立学校での学習内容(主 要科目)は1970年代の半分しかない。授業時間数も先進諸国の中で最低ランクだ。校内暴力、いじめ、自殺…何か問題が起こるたびに「偏差値教育」「詰め 込み教育」がヤリ玉に挙げられ、学習内容の削減が次々と実施されてきた。しかし、その施策が間違っていたことは明らかだ。子供たちの学力水準が低下の一途 を辿っていることは、各方面の調査機関によって指摘されている。また、それによって改善されるはずだった教育環境は、改善どころか徐々に悪化している。相 変わらず続く「不登校」「いじめ」問題に加え、学級崩壊とモンスターペアレントの出現、そして教師の精神疾患の増加が顕著になってきた。様々な要因が挙げ られるが、ここでは子供の変化と教師の変化に分けて原因を考えてみたい。
子供の変化について詳しく分析したのが内田樹氏の「下流志向」だ。昭和30年代を舞台とする映画がヒットしたが、あの頃の子どもは社会との関わりを「労 働」から始めた。家のお手伝いをし、おつかいにも行った。そして、母親から感謝され、父親から褒められ、時にお小遣いを貰うことで労働の喜びや尊さ、社会 の仕組みを自然と学んだ。
一方、日本が豊かになると子供は「労働」をしなくても「お金」が手に入るようになった。物心ついた時には自分名義の通帳が存在し、小学校入学前に数十万円 の貯金を持っている子も珍しくない。また、小さい頃から「お小遣い」をもらうことを当然の権利として有している。そのため、彼らは社会との関わりを「消 費」から始めることになる。言い換えると、昔の子どもが「ボランティア」から社会生活を始めたのに対して、今の子供は「ビジネス」から始めるのだ。する と、自然と「費用対効果」を学ぶことになる。買ったジュースが不味いと感じた場合、二度と同じ商品を買うことはない。取引を停止する。
同じ現象が学校現場でも起こっている。多くの子供たちにとって、一時間じっと真面目に授業を受けるのは「苦痛」だ。彼らは苦痛という対価を支払っていると 感じている。それに見合うだけの「商品」が提供されない場合、取引を停止する。それが授業崩壊であり、不登校だ。ビジネスから社会との関わりを経験した彼 らにとって、ごく自然な行動だ。ボランティアから学んだ昔の子供が、見返りもなく苦痛を払うことを当たり前と捉えていた時代とは違ってしまったのだ。
教師側の変化としては、教育の現場からリーダーシップが消滅したことが大きい。リーダーシップとは組織の上に立ち、全体のモチベーションを上方へ引っ張り 上げる「力」のことだ。教育の現場で言うと「子供たちの(広い意味での)学習意欲を向上させる力」だ。それは「権威」と言い換えてもいいだろう。かつての 教師は聖職と呼ばれ、子供たちはもちろん、保護者もその権威を尊重し、教師自身も権威に相応しい自制心と向上心を備えていた。そうしたバランスの上に世界 最高と評される日本の教育制度は成立していた。ところが1980年代以降、「子供の人権尊重」という美辞麗句の下に、教師自らが子供たちと同じレベルまで 降りてきてしまった。上から引っ張り上げるという苦役を放棄したのだ。今では「お友達先生」が全国の学校に氾濫している。学校現場では長く「競争の否定」 が続き、悪平等主義とも言うべき指導が行われてきた。ついには、教師と生徒との間にあるべき「師弟関係」という格差までも解消してしまった。リーダー不在 になると、モチベーションを上昇させるエネルギーが消失する。すると、組織の中で負のエネルギーが発生し、全体を巻き込み、組織崩壊を起こす。学級崩壊は こうして生まれる。モンスターペアレントを生み出した原因も同じだ。教師が子供たちのレベルにまで降りてきてしまった以上、保護者から無理難題、クレーム が大挙して押し寄せてくるのも当然だ。
つまり、社会の変化、子供たちの変化に全く逆行する方向へと公教育が変節してきたことが、日本の教育が内蔵する最大の問題点なのだ。